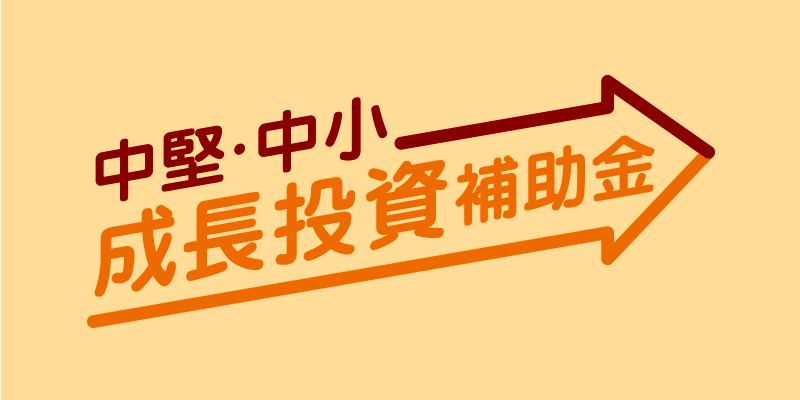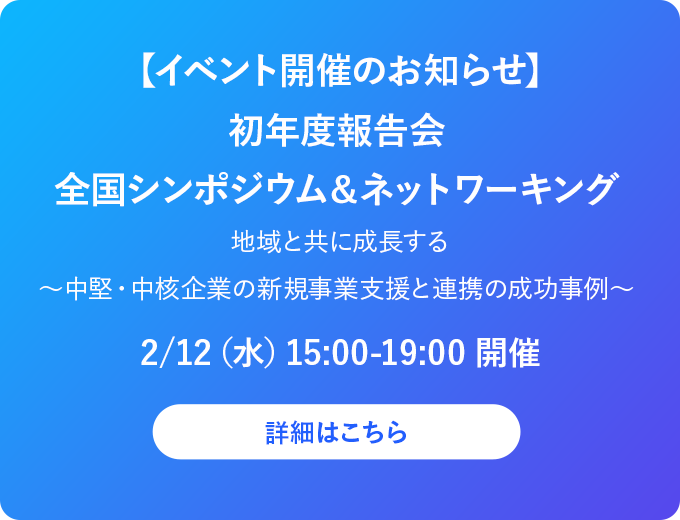令和7年度「中小企業支援事業補助金(中堅・中核企業の経営力強化支援事業)」
に係る補助事業者の公募について
【公募概要】令和7年度「中小企業支援事業補助金(中堅・中核企業の経営力強化支援事業)」に係る補助事業者を、以下の要領で募集します。 【事業内容】本事業は、地域経済を牽引する中堅・中核企業の経営規模拡大に伴う新事業展開等の取組を支援し、地域経済の持続的な成長を実現することを目的とし、中堅・中核企業に対し、ノウハウの獲得、地域内外とのネットワーク構築といった面を集中支援することで、経営規模拡大に伴う新事業展開等の取組を推進することで、企業の成長および良質な雇用の創出を行うものです。(1)支援プラットフォームの構築および支援対象企業の課題発掘・支援ニーズの把握(2)地域内外の支援機関等とのネットワーキングおよびマッチング支援(3)重点支援企業へのハンズオン支援(4)専門家ネットワークの活用(5)地域未来牽引企業の参画を推進する取組(6)事務局及び地域円卓会議との連携 ※詳細な事業内容、要件等については、後日掲載する公募要領をご確認ください。 【説明会】開催日時:令和7年4月25日(金曜日)14時~15時開催方法:オンライン会議形式(Microsoft Teams)参加方法:令和7年4月24日(木曜日)17時までに、下記【提出先、お問合せ先】に以下記載の上、お申込みください。 ・所属組織及び所属部署名・担当者名・連絡先(電話番号およびE-mail アドレス) ※事務局にて申込み受付後、入力いただいた担当者メールアドレスに対して、説明会のTeams URL等の案内メールをお送りします。メールが届かない場合は、事務局までご連絡ください。 ※公募説明会の動画は後日、本ページに掲載予定です。 【公募期間】令和7年4月23日(水)~令和7年5月15日(木)17時必着 【提出先、お問合せ先】中堅・中核企業の経営力強化支援事業事務局執行管理団体 株式会社JTB電話番号:03-5539-5247メールアドレス:shien2@bsec.jp営 業 時 間:平日10時~17時(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)事務局HP:https://chiiki.platform.go.jp/ 【ダウンロードファイル】・公募要領・申請書様式・交付規程 【参考:令和6年度の事業成果】・令和6年度 報告会 レポート・令和6年度 取組事例集・企業支援事例集