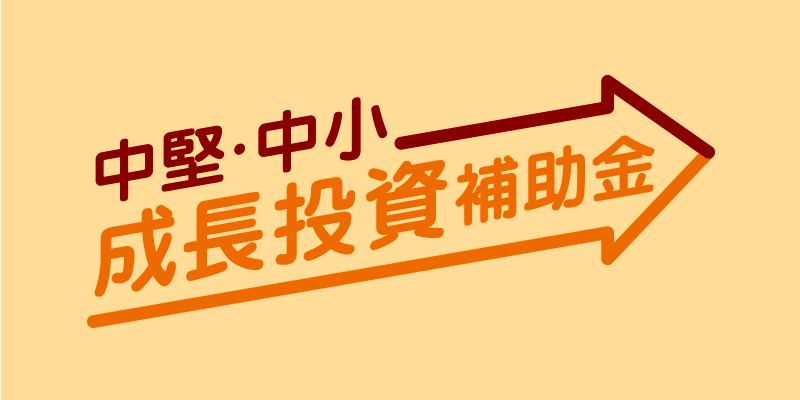全国21拠点のプラットフォームが切り拓く成長戦略。中堅・中核企業支援事業 初年度報告会 レポート

経済産業省では地域の中堅・中核企業の成長促進のため、地域・テーマごとにプラットフォームを全国に21拠点立ち上げ、新規事業の展開等を支援しています。初年度の取り組みの総括としてシンポジウムを開催し、本事業の支援によって生まれた好事例を紹介しました。また、シンポジウムの後半ではトークセッションを行い、オープンイノベーションや多様なステークホルダーとの協働による企業成長について、事例やノウハウを紹介。今後の中堅企業や支援機関の在り方について、方向性を提示した。
中堅・中核企業を支援するプラットフォーム、その役割とは
第一部の冒頭は、経済産業省 地域経済産業政策統括調整官の宮本岩男氏による開会の挨拶が行われた。
宮本氏は政府の中小企業支援について、企業が成長すると支援が急減することが課題になっていると現状の問題点を指摘。この課題解決のために、従業員2000人以下の企業を「中堅企業」と定義し、関係省庁が支援策を充実させる動きが開始した。

続いて今年度の実績について触れ、「経済産業省による中堅企業支援の初年度で、全国21の事業者が支援活動を展開し、284社がセミナーに参加、126社が具体的な支援を受けました」と成果を報告。最後に「政府は今後も中堅企業支援を強化し、地域経済の成長を促進する方針を示しています」と今後の展望を語り、挨拶を締めくくった。
続いて、PwCコンサルティング合同会社の千葉史也氏が、中堅企業の成長支援に関する取り組みについての説明を行った。
千葉氏はまず中堅企業の役割について再定義する。「従業員2,000名以下で大企業と中小企業の中間に位置する企業であり、成長力・変革力・社会貢献力が期待されています」と述べ、経済産業省が中堅企業の新分野進出や事業拡大の重要性を強調していることにも言及した。

本事業では、中堅・中核企業の新事業展開や経営力強化を支援するためのプラットフォームを全国21拠点に設置しています。地域型は北海道から沖縄まで14拠点、テーマ型は医療、製造、半導体など特定分野に特化した7拠点が設けられました。プラットフォームの主な役割として、企業の課題把握と未来志向のリーダーシップ醸成によるマインドセット形成、新規事業の計画策定と社内外の橋渡しを行うコーディネート機能、社内リソース不足を補う専門家紹介や伴走支援などのソリューション提供の3点。
事業の成果については、2025年1月時点で84社が新事業計画を策定しており、今後さらに増加する見込みだという。千葉氏は最後に「この事業を通じて中堅企業の成長を支援し、新規事業の成功体験を積み上げることで、中堅企業のさらなる発展を促進していきます」と意欲を示した。
取り組み事例の紹介では地域型プラットフォームの運営事業者やテーマ型プラットフォームの運営事業者として5つの企業・団体が登場。各事業者のプレゼンテーションについては、以下の動画にて一部始終を公開している。


第二部では、トークセッションを開催。「未来への共創(地域との連携やオープンイノベーション、多様なステークホルダーとの協働による企業成長)」をテーマに、中堅企業が新規事業に取り組む際の課題や支援について、経営者2名と支援機関2名でディスカッションを行った。
登壇者は、シナノケンシ株式会社 代表取締役社長 金子行宏氏、ヤマモリ株式会社 常務執行役員 前田博文氏、株式会社北海道共創パートナーズ 代表取締役社長 岩崎俊一郎氏、PwCコンサルティング合同会社 パートナー 大橋歩氏。モデレーターは名古屋商科大学ビジネススクール教授 慶應義塾大学名誉教授の磯辺剛彦氏が務めた。

磯辺氏:私自身、2014年に「中堅企業研究会」を立ち上げ、中堅企業の成長可能性と地域経済における重要性を感じていました。強い中堅企業は新規事業に挑戦する傾向がありますが、それを軌道に乗せるには従来の常識を打破する必要があります。

磯辺氏:まずは金子さんからシナノケンシ株式会社が新規事業に取り組んだきっかけについて教えていただけますか。
金子氏:当社は長野県に本社を置く100年以上の歴史を持つ企業で、小型精密モーター開発・製造が主力事業です。
新規事業に取り組んだのは、急速な市場変化と技術革新への対応、持続的成長の継続が主な理由です。当社は過去にも事業転換を成功させてきました。製造業における人手不足解決のための、自動搬送ロボットの開発や、既存のモーター技術を活かすべくスタートアップと連携し、人工衛星の姿勢制御装置の開発などを行ってきました。宇宙市場やロボット市場の開拓に取り組んでいます。
新規事業を進めるにあたり、3つの課題がありました。1つ目は既存事業と新規事業のバランスの取り方です。既存事業のリソースを使うため、社内の理解を得ることが重要になります。そのため、当社では目標や計画を明確にし、新規事業の価値を伝えることで社内の納得感を高めるようにしながら取り組んできました。
2つ目は新規事業と既存事業とでは考え方が違うことです。そのため、いかにマインドセットに変革を起こしていくかが重要になります。これに対しては組織や管理を分け、意思決定権を明確に切り分けました。
3つ目はいかにしてオープンイノベーションを推進していくかということです。これは、スタートアップや他の新規事業チームとの協業を積極的に行うことで解決しようとしています。いずれにしても、市場の変化が急速に進む現代社会においては、何もしないことが一番大きなリスクだと思っています。

磯辺氏:ありがとうございます。日頃、中堅企業を支援する立場にいる岩崎さんにお聞きしたいのですが、新規事業を立ち上げる際にはどのようなことが障壁になるのでしょうか。また、それに対してはどのような支援が有効になるのでしょうか。
岩崎氏:当社は北洋銀行の100%子会社として2017年に設立され、コンサルティングやファンド運営、スタートアップ投資を行い、特に道内中堅企業の新規事業立ち上げを支援しています。
これまで中堅企業から相談を多く受けてきましたが、その中で特に感じているのは「ゼロイチの壁」です。つまり、新たな事業を生み出せないのです。特に歴史のある企業では組織の論理によって新規事業が骨抜きにされがちで、企画段階で社長や役員から厳しく詰められ、進捗が遅れるケースが多い。これに対しては明確な方針の策定が必要であり、私たちのような外部の支援機関としては、時間軸の明確化をサポートすることが重要だと考えています。

磯辺氏:大橋さん、オープンイノベーションを推進したいと考えている企業に対しては、どのような支援が有効なのでしょうか。
大橋氏:新規事業の課題として「専門性の欠如」と「人材不足」があります。新事業では社内に専門知識が不足しがちで、また既存事業から人材を割くと人手不足が生じます。オープンイノベーションで産学官連携などを通じて外部知見を取り入れることが効果的です。
従来のオープンイノベーション推進はネットワーキングの支援が中心でしたが、現在はより戦略的な関係構築が求められています。特にスタートアップとの協業では、文化の異なる価値観であることが多いため、近年は実際にサービスを試しながら協業の方向性を模索するアプローチが注目されています。単なる連携ではなく、計画段階から地道な取り組みを行うことが成功の鍵となるのではないでしょうか。

磯辺氏:なるほど。醤油の老舗企業であるヤマモリ株式会社では、新規事業にどのように取り組まれたのでしょうか。
前田氏:当社は三重県桑名市に本社があり、1889年創業の企業です。醤油醸造で創業し、1969年に日本初の釜飯レトルト食品を製造・販売、1996年にタイへ進出しました。私は三菱UFJ銀行で30年勤務後、2019年にヤマモリに出向し、現在は営業本部長として事業構造改革に取り組んでいます。
新規事業に関しては、銀行員としての経験を活かし財務視点から経営課題を分析し、危機感を持って取り組みました。従来のOEM中心から脱却し自社ブランド構築と収益向上を目指すため、5年前に事業再構築プロジェクト「YTA」を立ち上げました。既存のGABA技術を活用した酢飲料で自社ブランドを確立し、しょうゆ油を利用した生分解性プラスチックの研究も大学と共同で進めています。短期的収益だけでなく長期的成長を見据えた事業開拓をしています。

磯辺氏:長い歴史を持つ企業は、時間の経過とともに硬直化やマンネリ化が生じやすいとも考えられます。特に家族や親族がオーナーとなっている企業が新規事業や組織変革に取り組む際、どのようなことがポイントになるのでしょうか。
岩崎氏:経営トップが新規事業やM&Aについて具体的に考え、社員に明確に伝えることが重要です。多くの企業は中期経営計画でこれらを掲げますが、具体的戦略がないことが少なくない。掛け声だけで終わらせず、経営陣自らがビジョンや目的を明らかにし、自分の言葉で語れるようにすることが必要であり、支援事業者もその点を促すべきだと考えています。
磯辺氏:先ほど前田さんのお話では、ヤマモリで既存技術を活かして新ブランドを立ち上げたことに触れられていました。既存技術を新規事業に活かす場合、発想の転換や従来の事業とは異なる進め方が求められることが多々あります。変化についていけない従業員も多く出てきてしまうことが新規事業の障壁になることもありますが、こうしたことについてはどのような支援が有効でしょうか。
大橋氏:経営者がリスクを取りながら意思決定を行い、組織全体でムーブメントを作ることが重要です。しかし、そういった内部の意識改革や行動変容を行わないまま、ただただ補助金など資金を投入してしまうと、多くの場合は失敗に終わってしまいます。だからこそ、経営者の強いコミットメントとともに、信頼できるパートナーを見つけ、困難を乗り越えることが成功の鍵となります。
私たちのような支援機関がすべきことは、客観的な立場から経営者や組織との関係構築に尽力し、自らの強みを可視化する機会を促すこと。これにより多くの連携や協力の機会を得られるようになります。
磯辺氏:新規事業への取り組みの際に重要なことなど、経営再建に臨む中堅企業にとってヒントとなりそうなエピソードがたくさんありました。皆様、本日はどうもありがとうございました。


シンポジウム終了後にはネットワーキングの時間を設け、参加者・登壇者・プラットフォームの運営事業者が交流を行った。
本事業の初年度の取り組みの紹介や、中堅企業が抱える課題を深掘りしたトークセッションを通じて、中堅企業の成長を助けるさまざまなヒントを示した会となった。