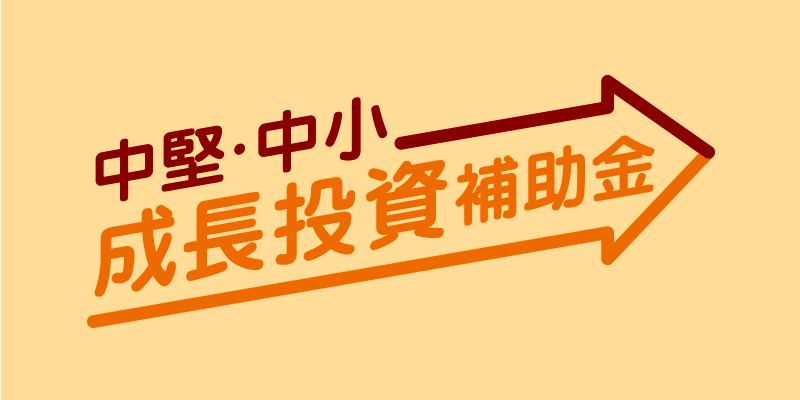精密部品メーカーとアニメ会社が協力?
攻めのブランディングに裏打ちされた、松尾製作所の確かな技術力

ハイブリッド車やEVの普及、さらには自動運転や移動手段をサービスとして捉えるMaaS(Mobility as a Service)の進展など、「100年に一度」とも言われる変革のときを迎えている自動車業界。
自動車部品メーカーに求められる技術も同様に変化し、EVは従来のガソリンエンジン車とは使用する部品が大きく変わり、需要が激減する部品が多々。もとよりクルマ一台に必要な部品は3万点と言われるが、EVは2万点ほどに過ぎないからだ。
こうしたパラダイムシフトに対応できず、撤退を余儀なくされる企業も少なくない中で、気を吐くのが愛知県に部品生産工場を構える松尾製作所だ。EV車はもちろん、その他の産業装置にも不可欠なセンサー「レゾルバ」を新たに開発。他を圧倒する機能価値によって、先行企業の独壇場である市場に風穴を開けようとしている。
一体、どのようにしてレゾルバ開発に至ったのか? 変革期を絶好機に変えたのか? 同社における技術開発のトップである関冨勇治取締役に聞いた。
優れたエンジニア人材を集めるため、アニメを使う
松尾製作所のコーポレートサイトをはじめて覗いた人は、少し戸惑うかもしれない。なにせトップページからアニメキャラ風のイラストが大胆に配され、オリジナルアニメによる自社CMや製品PRの動画リンクも用意されているからだ。しかし同社は愛知県大府市に本社を構える、自動車用をメインとしたれっきとした精密部品メーカーだ。
創業は1948年。自動車用の線ばね製造から事業をはじめ、その後、金型でつくる板ばねや金属プレス製品も手掛けるようになった。さらに自動車用のホーンスイッチなどを樹脂部品まで手を広げ、今は電気回路を使った精密部品なども多く生産している。売上は右肩上がりで、直近の2023年はグループ全体では700億円を超えている。

取引先はトヨタ本体や部品メーカーなどトヨタループが5割以上。自動車業界は「ケイレツ」と言われるピラミッド構造が根強く、自動車メーカーと取引するティア1から、ティア2、ティア3とサプライヤーのピラミッド構造がある。
「弊社は、その中のティア2に属していますが、自動車メーカーからのお声がけも多い。なので自らを『ティア1.5』と呼んでいます」と関冨勇治取締役は笑う。冗談めかして「ティア1.5」を自称するのは、単にケイレツのレールにのってものづくりをする部品メーカーとは、ひと味違うためだ。
自動車部品メーカーは急速に進んだハイブリッド車やEVへのシフトの影響で、競争が激化している。これらはガソリンエンジン車に比べて1万点も部品数が少なくなるため、需要が激減する部品も多いからだ。特にケイレツ意識が根付き過ぎ、発注通りのものづくりに慣れすぎたティア2以降の中小部品メーカーには苦戦する企業も少なくない。
しかし、松尾製作所はこの波に柔軟に対応することで売上を伸ばし続けてきた。そもそも設計から試作、量産までの一貫生産体制があるため、臨機応変にものづくりができる。加えて「可能性、改善、進歩を追求すること」の社是に従い、今いる場所に満足せず、常にチャレンジングなことに足を踏み入れるカルチャーが染み付いているためだ。
「EVシフトによって自動車部品のサプライチェーンも変化。これまでの取引先はもちろん、付き合いのなかったところからも『こういうものが作れないか?』と相談がくるようになりました。弊社のエンジニアはそうしたお声がけに、むしろ積極的で、かつ着実なものづくりで返してきた自負があります。『松尾につくれないものはない』と言われるゆえんです」
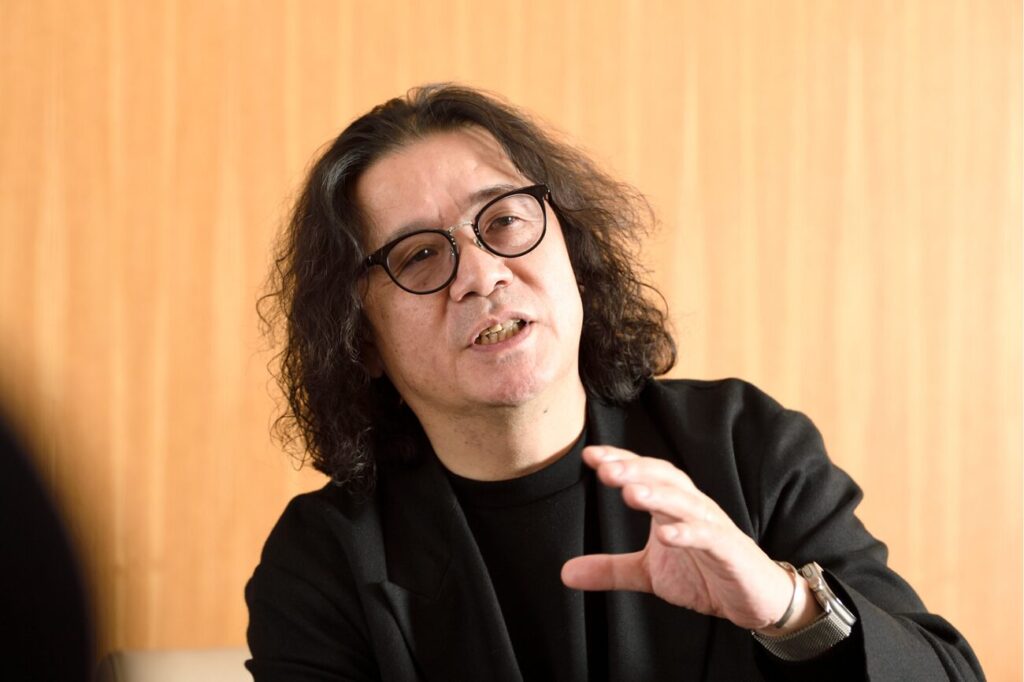
高いエンジニア力の源泉にも、改善や進歩を重んじる社是がにじむ。本来業務だけではなく、技術者の知見を磨くことを積極的に奨励している。特に既製品を分解してその構造を研究する「リバースエンジニアリング」に力を入れてきた。
「2010年代からはEVのモーターやインバーターの分解を積極的に行っています。中でもアメリカ、ドイツ、中国など日本以外のメーカーを積極的に扱い、これまで30車種ほど分解してきました」
EVの分解は、もともと技術系専門誌の企画として、出版社の依頼を受けて始めたもの。その後、発表された誌面リポートの質の高さから、企業や大学の研究機関からも「このモーターも分解してほしい」「あのインターバーも調査してほしい」と依頼が殺到するようになったという。
結果として、世界有数の「EVに関する解体分析・調査」の実績を持つ企業になった。どのサプライヤーより各メーカーのEVにどんな部品が実装されているか、最適化されているか、知見を蓄積させているわけだ。
「特に若手エンジニアを分解・調査の現場に立たせています。3DCADからでも情報は得られますが、実際にモノを触って、分解する情報量の豊かさにはかなわない。先端のEVの現場の部品構造を一発で学べますからね」
エンジニアの育成同様に採用にも力をもちろん入れている。またここでも「進歩を追求」しているようだ。冒頭に触れた、アニメキャラを配したウェブサイトや、会社説明・商品説明のアニメによる告知活動は、「アニメによってわかりやすくハードル低く自社を伝える」ため。そして認知度をあげるとともに、潜在的に優秀な若手エンジニアをリクルーティングするための施策だという。
「アニメ好きな方のなかには、ものごとを突き詰めて邁進する傾向が高い。いわゆる“オタク気質”であることは、良いエンジニアになる素養があると考えているからです」
こうしてEVシフトを起点に変革してきた自動車業界。松尾製作所は柔軟に技術を磨き、対応してきた結果生まれたのが、次世代車両向けの回転角センサー「レゾルバ」だ。
イノベーティブな製品開発だけでは、成功しない。
レゾルバそのものは、新しい製品ではない。回転物の回転角度を電気信号に変えて速さと角度を検出するアナログのセンサーで、モーターなどに多く使われてきた。
電磁鋼板の芯にコイルを巻いたシンプルな構造で強度が高く、過酷な環境でも正確なセンシングができるのが特徴だ。そのため建設機械や産業機械のモーターには欠かせない部品になっている。昨今、このレゾルバが多く使われ、急激に需要を伸ばしている領域が「EVのモーター」である。EVが航続距離を伸ばすには、モーターを効率的に回す必要がある。そのためには正確なモーターの制御が不可欠で、角度と回転数を計測するレゾルバは、要の部品というわけだ。

「EVシフトが進む中、レゾルバの需要があがることを肌身で感じていました。ばねからはじまった弊社のものづくりの技術も活かせる。そこで十数年前から独自レゾルバの開発に着手しました。本業とは別に、こっそりと私ひとりで就業後に手がけ始めたのがスタート。いわばB面でこっそりとはじめたのです」
もっとも、EV用レゾルバはすでに先行企業が圧倒的なシェアを誇っていた。同じものをつくっても勝ち筋はない。そこで同社が目指したのが「軽さ」だった。部品の軽量化もEVの航続距離を伸ばすことに直結する。軽量化のために使う材料が減れば、カーボンニュートラル化にも寄与できる。
では、どのように軽量化を果たしたのか?着目したのは、物理現象の「表皮効果」。磁束が磁性体を通るとき、磁性体の表面は磁束密度が高いが、表面から離れると低くなる特性がある。ひらたくいえば、磁性体のサイズが変わっても、流れる磁束は表面ほど高く、分厚くしてもさほど変わらないということだ。これを「表皮効果」という。
「そこで『レゾルバも表面部分に大半の磁束が流れているはずだ』と仮説を立てました。従来のレゾルバは、ステーターと呼ばれる電磁鋼板を積層させた部品にコイルを巻いてつくられている。しかし、積層する必要はなく、電磁鋼板を曲げて磁気回路を構成したステーターにコイルを巻けば、軽くしたうえで従来と同様の測定ができると考えました」
たった一人ではじまったプロジェクトは、数年の時を経て数名のプロジェクトになっていた。
「途中は、『そんなものつくって売れるのか?』と訝しがられましたけどね(笑)。言われながらも、挑戦を奨励するカルチャーは根付いていたし、当時副社長だった松尾(基)社長も、一緒に手伝ってくれたのは心強かった」
そして開発されたのが、薄いながらもコの字型にすることで強度を担保した独自構造のステーターを積んだレゾルバだ。従来品と比較して77%も部材を減らし、軽量化を果たすことにも成功した。

もっとも、松尾製作所がすごいのはここからだ。
「いくらイノベーティブな製品ができても、我々のような中堅企業がそれだけで成功するのは難しい。大企業と比べて認知も低いですから。『表面にしか磁束が流れないので、この軽量なレゾルバで十分に測定できるんです!』とプレゼンしても、そもそも聞く耳をもってもらえない。もとより、磁束は目に見えませんからね」
そこで関冨取締役は大学を味方につけるべく動き出した。岐阜大学の工学部に声をかけ、「レゾルバの表皮効果を考慮したユニット搭載時の性能をシミュレーションするソフト」の開発を成し遂げた。
「多くの大学は産学連携に積極的で、企業に扉が開かれている。しかも新しい技術開発を一緒に手掛けるのは双方にとって魅力的です。私のモットーである『足と笑顔と図々しさ』で、直接交渉してご協力いただきました」
そして東北大学と開発した機器によって、軽くとも従来以上に正確に測定できるレゾルバを測定データとともに発表。すると潮目が変わり、企業から問い合わせや打診が入るようになったのだ。買い手となる自動車メーカーや大手部品メーカーのエンジニアたちは、むしろ「実績よりメカニズム」でものごとを判断する。技術的なエビデンスがとれた新型レゾルバは、EV用モーターとして“使える”と認知された瞬間だった。
2025年にはいよいよ某メーカーの新型EVに実装されるという。先行企業の牙城を松尾製作所が切り拓く先鞭になりそうだ。
「ティア1.5を超えていきたい。かつてインテル製のCPUを搭載したPCを『インテル・インサイド(インテル入ってる)』と付加価値がついていったように、『松尾インサイド』とメーカーが誇りたくなるようなブランドを目指したいですね」
ものづくりの延長線上に、宇宙とアニメが見えてくる。
根付いたエンジニアリングの高い技術を、「可能性、改善、進歩を追求すること」の社是に従って、追求する――。新型レゾルバの開発に結実したその姿勢は踏みとどまることなく、常に一歩先、二歩先を歩み続けている。
現在、さらに磨きあげたシートレゾルバという薄いセンサーを開発中。シートレゾルバは現状直径12mmだが、これを直径5mmまで小さくさせる予定だという。
「さらに軽量化や小型化が進むと、EVや産業用機器のみならず、ロケットや人工衛星など宇宙関連の用途も開かれる。また医療用手術器具などにもニーズがあります。モビリティ以外の市場が多彩に開く」
モビリティ領域も近い将来実現するであろう、MaaSへの意外な準備が進歩を追求する、松尾製作所らしい。
実は、リクルーティングや認知度アップの目的で展開しているアニメなどのコンテンツ戦略。実はこれは昨年M&Aで子会社化したアニメ制作会社によるものだ。外部に発注する術もあったが、「可能性」を感じたからこその施策だという。
「テスラを乗ったことがある方なら実感されていると思いますが、インパネの中央に大型モニターがあるだけのシンプルなつくりです。自動運転が本格化していくと、これまでのような運転そのものを楽しむ体験から、車内エンターテイメントを楽しむようになっていくと考えられます。アニメは世界に冠たるコンテンツですから、何かしらアニメを使ったコンテンツやサービスは、SaaSになったら注目されるはずです。一見、関連のないビジネスにように見えるかと思いますが、私たちのものづくりの姿勢と矛盾していないんですよ」
パラダイムシフトを好機にしてきたのは、こうした飽くなき挑戦心と、柔軟なビジョンのなせる技に違いない。ここまで読まれた方ならば、松尾製作所のオフィシャルサイトの見え方が変わってくるはずだ。ポップなデザインの裏には、中堅企業が成長するヒントと、持つべき姿勢が隠されているのだ。