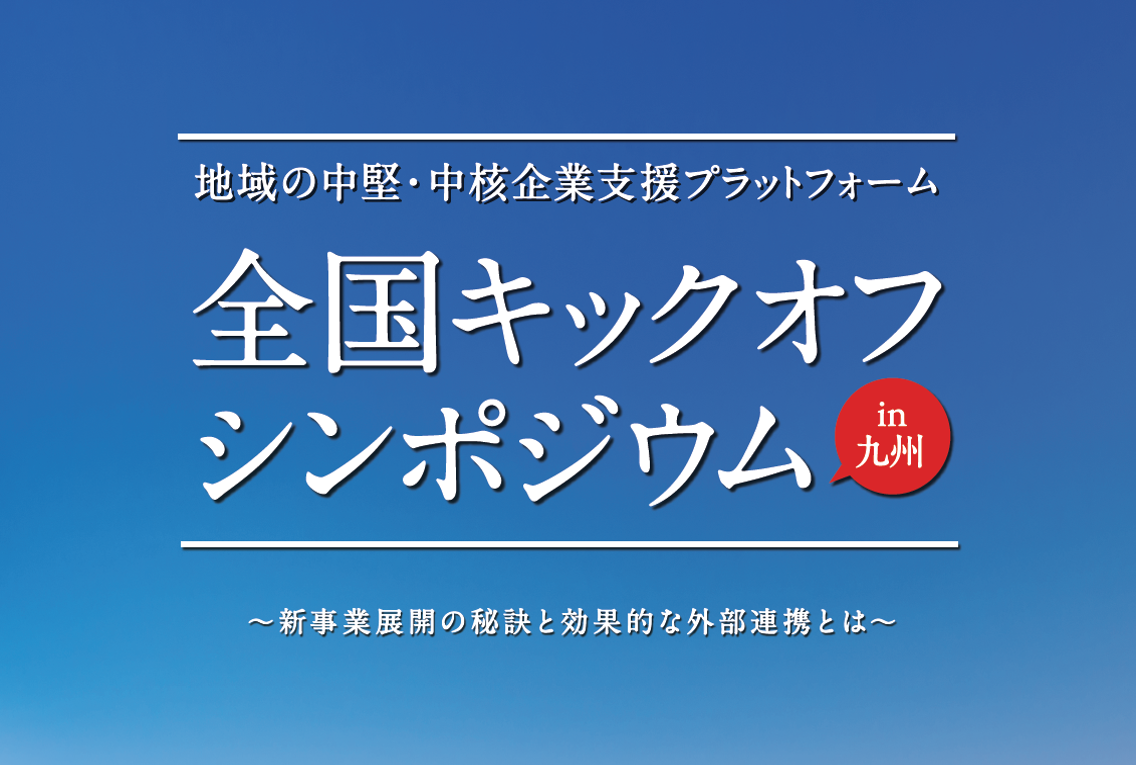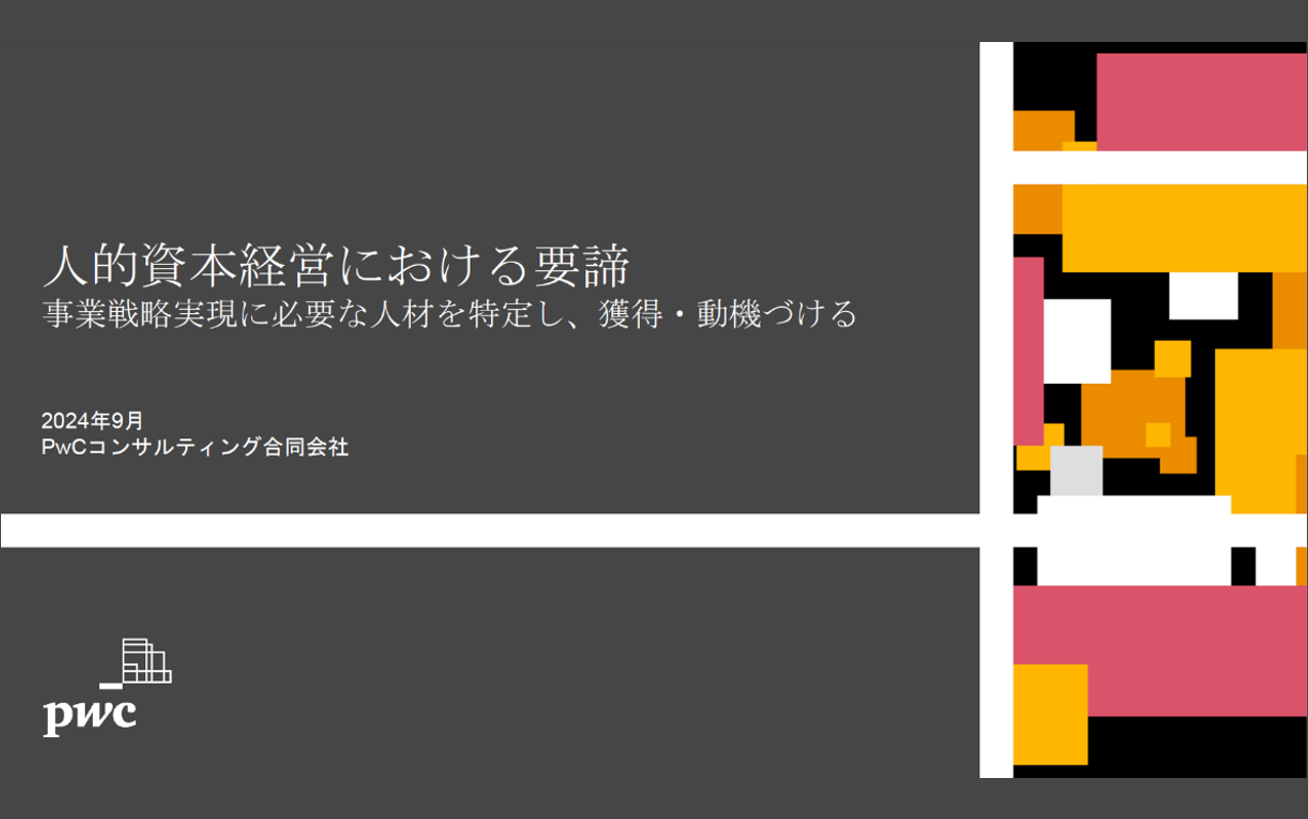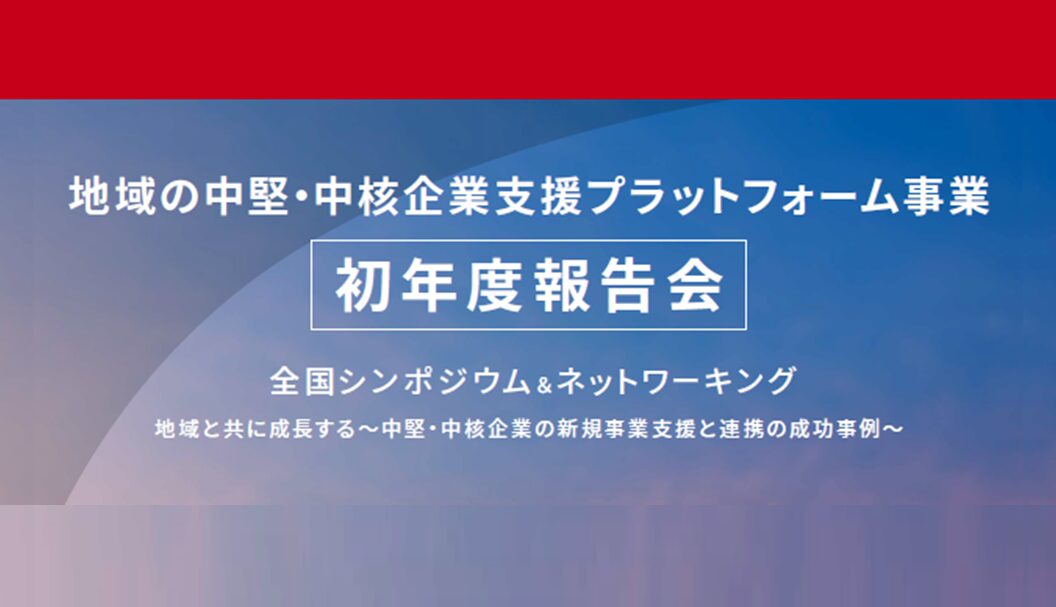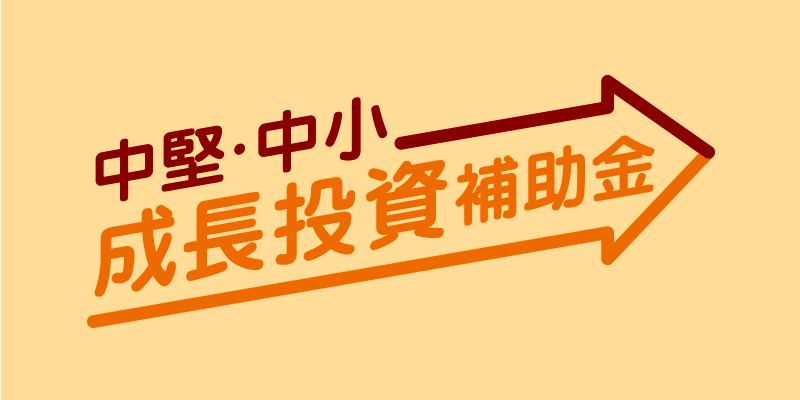全国21拠点のプラットフォームが切り拓く成長戦略。中堅・中核企業支援事業 初年度報告会 レポート
経済産業省では地域の中堅・中核企業の成長促進のため、地域・テーマごとにプラットフォームを全国に21拠点立ち上げ、新規事業の展開等を支援しています。初年度の取り組みの総括としてシンポジウムを開催し、本事業の支援によって生まれた好事例を紹介しました。また、シンポジウムの後半ではトークセッションを行い、オープンイノベーションや多様なステークホルダーとの協働による企業成長について、事例やノウハウを紹介。今後の中堅企業や支援機関の在り方について、方向性を提示した。 中堅・中核企業を支援するプラットフォーム、その役割とは 第一部の冒頭は、経済産業省 地域経済産業政策統括調整官の宮本岩男氏による開会の挨拶が行われた。 宮本氏は政府の中小企業支援について、企業が成長すると支援が急減することが課題になっていると現状の問題点を指摘。この課題解決のために、従業員2000人以下の企業を「中堅企業」と定義し、関係省庁が支援策を充実させる動きが開始した。 宮本岩男|経済産業省 地域経済産業政策統括調整官 続いて今年度の実績について触れ、「経済産業省による中堅企業支援の初年度で、全国21の事業者が支援活動を展開し、284社がセミナーに参加、126社が具体的な支援を受けました」と成果を報告。最後に「政府は今後も中堅企業支援を強化し、地域経済の成長を促進する方針を示しています」と今後の展望を語り、挨拶を締めくくった。 続いて、PwCコンサルティング合同会社の千葉史也氏が、中堅企業の成長支援に関する取り組みについての説明を行った。 千葉氏はまず中堅企業の役割について再定義する。「従業員2,000名以下で大企業と中小企業の中間に位置する企業であり、成長力・変革力・社会貢献力が期待されています」と述べ、経済産業省が中堅企業の新分野進出や事業拡大の重要性を強調していることにも言及した。 千葉史也|PwCコンサルティング合同会社 本事業では、中堅・中核企業の新事業展開や経営力強化を支援するためのプラットフォームを全国21拠点に設置しています。地域型は北海道から沖縄まで14拠点、テーマ型は医療、製造、半導体など特定分野に特化した7拠点が設けられました。プラットフォームの主な役割として、企業の課題把握と未来志向のリーダーシップ醸成によるマインドセット形成、新規事業の計画策定と社内外の橋渡しを行うコーディネート機能、社内リソース不足を補う専門家紹介や伴走支援などのソリューション提供の3点。 事業の成果については、2025年1月時点で84社が新事業計画を策定しており、今後さらに増加する見込みだという。千葉氏は最後に「この事業を通じて中堅企業の成長を支援し、新規事業の成功体験を積み上げることで、中堅企業のさらなる発展を促進していきます」と意欲を示した。 取り組み事例の紹介では地域型プラットフォームの運営事業者やテーマ型プラットフォームの運営事業者として5つの企業・団体が登場。各事業者のプレゼンテーションについては、以下の動画にて一部始終を公開している。